この記事では「AviUtl」本体と「拡張編集プラグイン」のダウンロード・インストール方法について解説していきます。
他のサイトでダウンロードできなかったという人も「この記事でできた!」という声を多数頂いておりますので御覧ください。
【注意!他のサイトで2024最新版!と書いていて更新されてない記事が非常に多いです。この記事はしっかりと最新版に対応しており、わかりやすく説明していきます。】
そもそもAviutlって何?
無料で動作の軽い動画編集ソフトです。
無料のソフトですが、慣れれば有料ソフト並みの動画を作成することが簡単なうえ、編集も簡単なので初心者から上級者まで扱うことができます。
また、個人で作られたものなので制限や課金要素もないしオフラインでもちろん使用できます。
Aviutlのダウンロード
Aviutlはいろいろダウンロードするものが多くわかりにくいので
初めてPCを買った状態からでもめちゃくちゃわかりやすく説明していきます。
Aviutlの置き場所を作ろう
Aviutlを保存するフォルダを開きます。

矢印先にある、フォルダをクリックすると「エクスプローラ」が開きます。

エクスプローラーが開いたら、「PC」→「Windows(C:)」を選択します。
(ここでCの容量がなくDドライブがあれば、そちらを使ってもいいですが「Cドライブ」とか「Dドライブ」のことがよくわからない人はこのまま進めてください)

Cドライブを開いたら空いているスペースを「右クリック」→「新規作成」→「フォルダ」を選択します。

フォルダ名は「Aviutl」にしましょう。
AviUtl本体 & 拡張編集プラグイン のダウンロード・インストール
これから「Aviutl本体」と「拡張編集プラグイン」をダウンロードします。
拡張編集プラグインを入れると高度な編集ができるようになります。
いやいや、そんな高度な編集しないし…と思った方。
Aviutl本体だけの編集機能は笑っちゃうほどに使えませんので、必ずダウンロードしましょう。
AviUtl本体&拡張編集プラグイン ダウンロード
Aviutlのお部屋でAviUtl本体&拡張編集プラグインをダウンロードします。
(404エラーが出る場合はリンクのhttps://をhttp://に変更してください。)

ちょっとした注意!
拡張編集プラグインの説明に (AviUtl、拡張編集ともに初めてな方は下のOmakeにある拡張編集セットを使うと導入が少し楽です) とありますが、最新版ではないためおすすめしません。
一番新しいバージョンをクリックするとダウンロードが始まります。

AviUtl本体&拡張編集プラグイン インストール
このようにダウンロードできたら、クリックして「デスクトップに解凍」してください。
(このような表示がなかったり消えた場合は、エクスプローラーの「ダウンロード」フォルダの中にあると思います。)
もし、PCを買ったばかりや解凍ソフトをダウンロードしていないために解凍ができない場合はこちらの記事を参考にしてください。
【必須】誰でもできる!解凍ソフト「Lhaplus」ダウンロード方法
解凍できたら、ダウンロードした2つのフォルダーの「中身をすべて」前のステップで作成した「Aviutl」のフォルダーの中に入れましょう。

できたら、aviutl.exeを一度開いてみましょう。

開けることが確認できたら、上のタブの「設定」をクリック

その中の「拡張編集の設定」を見つけてクリックします。

このように、Aviutlとは別に拡張編集のウィンドウがでれば大丈夫です。
注意!
出ない方は、拡張編集がきちんと入っていないためもう一度見直してください。
絶対に入れてほしい拡張機能たちのダウンロード
入力プラグイン「L-SMASH Works」のダウンロード・インストール
入力プラグイン「L-SMASH Works」って?
AviUtlデフォルトの状態では「AVI」や「WAV」などの、限られた形式のファイルしか読み込めません。これではいちいち読み込む素材の形式を気にしないとならず、不便です。
そこで入力プラグイン「L-SMASH Works」を導入することで「MP4」や「MP3」など、さまざまな形式のファイルを読み込めるようにしていきます。
L-SMASH Works ダウンロード
GitHubから、L-SMASH-Works_revXXXX_Mr-Ojii_Mr-Ojii.zipをダウンロードします。(XXXXはバージョンです)



ダウンロードをするとブラウザによっては以下のようにエラーが出ますが「>」から「不審なファイルをダウンロード」をクリックして、ダウンロードを続けてください。
(拡張子(.zipや.pngなどのこと)が特殊なためこのようなエラーが出ます。ウイルスとかではないです。)

ダウンロードができるとこのように下記の5つのファイルがダウンロードフォルダの中にあるはずです。
- lwcolor.auc
- lwdumper.auf
- lwinput.aui
- lwinput64.aui
- lwmuxer.auf
これら5つを「Aviutl」が保存されているフォルダのなかに入れましょう。
Aviutlを立ち上げます。
(立ち上げたままの人は一度閉じてから開きましょう)
「ファイル」→「環境設定」→「入力プラグイン優先度の設定」を開きます。

ウィンドウが開いて一番下にL-SMASHがあれば大丈夫です。
(なければ下に持っていきましょう)

注意!
「L-SMASH Works File Reader」が表示されていない場合は、L-SMASH Worksが正しく導入できていません。
無理な場合はセキュリティーソフトをoffにするといいかも
出力プラグイン「x264guiEx」 のダウンロード・インストール
いよいよ、これで最後です。
初期状態のAviUtlではavi形式でしか動画の出力ができません。
様々な形式(mp4など)で出力できるように必ず入れましょう。
「x264guiEx」 のダウンロード
rigayaの日記兼メモ帳にアクセスします。
右のサイドバーに「x264guiEx 3.xx」があるので押してください。

Githubに飛ぶので最新版のx264guiEx 3.xx.zipをクリックしダウンロードしてください。

「x264guiEx」 のインストール
ダウンロードした中にあるファイルをすべてAviutlのファイルにうつします。

再度、Aviutlを開きます。(開いたままの人は一度閉じてね)
その他→出力プラグイン情報をクリックします。

ここに、「拡張x264~」と書かれていれば、インストール完了です。

バグ修正&機能追加プラグイン・patch.aulを導入
Aviutlは不便な点や、バグがたくさんありこのままでは不便です。
patch.aulは
- バグの修正
- やり直すコマンドの実装をはじめ、様々な機能の追加
- AviUtlの軽量化
と、たった1つで痒い所に手が届く超有能プラグインです。
必ずしも入れる必要はありませんが、入れるのと入れないのとでは処理速度に大きな違いがあるので、入れておくべきです。
patch.aulは
AviUtl本体のバージョン:1.10
拡張編集のバージョン:0.92
専用のプラグインです。
patch.aulをダウンロード
patch.aulのダウンロードサイトにアクセスします。

下にスクロールしてr43 謎さうなフォーク版XX(XXはバージョン)でXXの数字が一番大きいのが最新バージョンなので、そのセクションにあるzipファイルをダウンロード。


patch_rXX.zipを展開し、中身のpatch.aulだけをaviutl.exeと同じフォルダに入れるだけでOKです。
Visual C++ 再頒布可能パッケージ 2015-2022 X86をインストール
patch.aulの動作にはVisual C++ 再頒布可能パッケージ 2015-2022 X86が必要です。

Microsoftのページにアクセスし「Visual Studio 2015、2017、2019、および 2022」の項目にあるX86のリンクからダウンロードし、画面に従ってインストールをすれば完了です。
メモリ使用量を削減するプラグイン・InputPipePluginを導入
InputPipePluginはL-SMASH_Works File Readerを別プロセスで実行することで、AviUtlのメモリ使用量を削減してメモリ不足によるエラーを回避してくれるプラグインです。
これがあるだけで、エラーが出て作業がリセットされる…なんて悲劇を防ぐことができます!
InputPipePluginをダウンロード
InputPipePluginのダウンロードページから最新版をダウンロードします。


zipファイルを展開し、lwinput.aui と lwinput64.aui が置いてあるフォルダに
- InputPipePlugin.aui
- InputPipePlugin64.exe
- InputPipeMain.exe
を移動するだけでOK。
ちょっとしたいい話

メニューバーの「ファイル」→「環境設定」→「システムの設定」をクリックすると、上の画面が表示されます。
おすすめの変更点は4つ。

- 最大画像サイズを幅1920・高さ1080に変更
(大きいサイズの画像を端が切れることなく読み込みます) - リサイズ設定の解像度リストに1920×1080を追加
(1920×1080のxはエックスです。バツや乗算記号ではありません。) - 再生ウィンドウの動画再生をメインウィンドウに表示する にチェック
(ウィンドウの数が減って画面がスッキリします) - 編集ファイルが閉じられる時に確認ダイアログを表示する にチェック
(保存せずうっかり閉じてしまうミスを防ぎます)
変更した設定は、AviUtlを再起動することで反映されます。
以上でAviutlの設定が終わりです。お疲れさまでした。
なにかエラーや質問があればいつでもコメントかお問い合わせ下さい。
(twitterでもいいよ @kisaragi_2342)
Aviutlの使い方や編集技術についてもどんどん聞いてください。
要望が多ければ記事にします。
それでは。
ps.ガチで仕事で動画編集したいなら、Adobe契約したほうが良いよ。
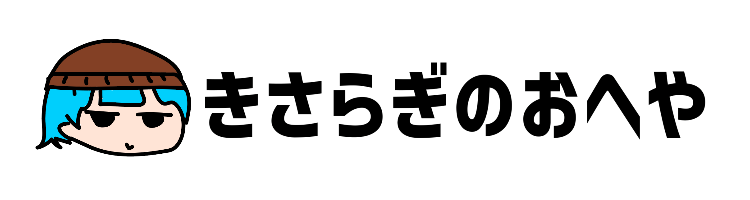







コメント